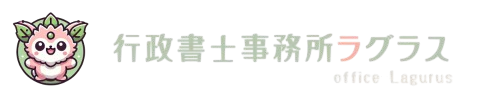物件選びの時に注意する点がいくつかあります。
申請までに立ち入り検査や届け出が必要なものがあるので十分注意が必要です。
(例)千葉県福祉のまちづくり条例
届出等手続き―特定施設(公益的施設等のうち特に公共性の高い施設)の新設・改修等にあたって届出が必要になります。
- 1.特定施設の新設・改修等
- 特定施設の新設、改修等をしようとする者は、着工前に知事に届け出る必要があります。
- 2.届出・内容審査
- 届出された内容が整備基準に適合しない場合、指導及び助言を行います。
- 3.着工
- 知事は、届出を行わずに着工をした場合に勧告及び公表をすることがあります。
- 5.公示の完了の届出
- 知事は、工事が届出の内容と異なり、かつ、整備基準に適合しないときは必要な措置を講ずるように勧告すことがあります。 また、勧告に従わないときは公表することがあります。
- 6.適合証の交付請求
- 公益的施設等が整備基準に適合している場合は、知事に適合証の交付を請求することができます。
- 7.適合証の交付
- 知事は、公益的施設等が整備基準に適合していると認めるときは適合証を交付します。
- 8.公表
- 知事は、適合証の交付を行った場合には、公表します。
※特定施設―児童福祉施設、共同住宅含む、公益施設等のうち特に公共性の高い施設
消防法施行令別表第1
| (6) | ロ | (4) | 障害児入所施設 |
| (5) | 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) | ||
| ハ | (4) | 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) | |
| (5) | 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
「障害者」―身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条第一項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
「障害児」―身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。
「障害区分」―障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。
「短期入所」―居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
「共同生活援助を行う施設」―障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。
| 防火管理者の選任 消防計画の作成 | |
| (ロ) | 10人以上 |
| (ハ) | 30人以上 |
| 消防機関の検査(使用開始届) | |
| (ロ) | すべて |
| (ハ) | すべて |
| 消火器 | |
| (6)ロ | すべて |
| (6)ハ | 延べ面積が150㎡以上 |
| すべての施設 | 地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が 150㎡以上 |
| スプリンクラー | |
| (6)ロ | 延べ面積275㎡以上 |
| (6)ハ | 延べ面積6000㎡以上(平屋以外) |
| 代替措置 | ・特定施設水道連結型スプリンクラー ・パッケージ型自動消火設備 |
| 自動火災報知機 | |
| (6)ロ | すべて |
| (6)ハ | すべて |
| 代替措置 | 特定小規模施設用自動火災報知設備(連動型警報機能付感知器) |
| 火災通報装置 | |
| (ロ) | すべて(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するもの) |
| (ハ) | すべて |
| 誘導灯 | |
| (6)ロ | 必須 |
| (6)ハ | 必須 |
| 避難器具 | |
| (ロ) | 20人以上(下階に飲食店・店舗・作業所などがある場合は10人) |
| (ハ) | |
| 非常警報器具 | |
| (ロ) | 20人~50人未満 |
| (ハ) | |
| 非常警報設備 | |
| (ロ) | 50人以上 |
| (ハ) | |
| 漏電火災報知器 | |
| (ロ) | 300㎡以上 |
| (ハ) | |
| 屋内消火栓設備 | |
| (ロ) | 700㎡以上(耐火構造・内装素材によって変わる) |
| (ハ) | |
| 防火物品の使用 | |
| (ロ) | すべて(カーテン、布製ブラインド、絨毯等の素材に燃えにくいものを使用したもの) |
| (ハ) | |
建築基準法 27条
次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する全てが当該特殊建築物から地上までの非難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
「特殊建築物」―学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
27条 別表(2)
| (い) | 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 3 共同住宅 |
| 6 福祉ホーム |
その他
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
〃 施行令
〃 施行規則
誘導基準省令
〃 施行細目 など