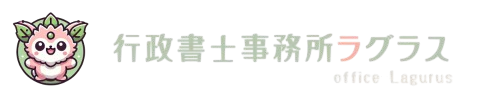虐待を受けた障害者の保護に対する協力について
居室の確保に関する協力
養護者による障害者虐待や、住み込みで働いてきた会社で飼養者による障害者虐待を受けた場合等で、放置しておくと障害者の生命や身体に重大なきけんをまねくおそれが予測されると判断された場合

市町村―緊急的な受け入れの要請
虐待を受けた障害者を保護するため
・契約による障害者福祉サービスの利用(短期入所、施設入所等
・やむを得ない事由による措置(短期入所、施設入所等)
により、養護者等から分離することがあります。
施設
正当な事由がない限りこれを拒んではならないと定められています。
知的障害者福祉法
(受託義務)
第二十一条 障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
身体障害者福祉法
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第一八条 2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。
保護された障害者への対応
職員は、保護された障害者が置かれている状況を理解し、受容的に関わり、不安や緊張を和らげるよう対応することが求められます。
身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて
身体拘束の廃止に向けて
障害者虐待防止法では「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。
やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。
緊急やむを得ない場合―支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に限定されます
1.やむを得ず身体拘束を行う場合の3要素
| 切迫性 | 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。 |
| 非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。 非代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。 |
| 一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。 一時性を判断する場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。 |
2.やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定する必要があります。この場合、管理者、サービス管理責任者、運営規定に基づいて選定されている虐待の防止に関する責任者等、支援方法について権限を持つ職員が出席していることが大切となります。
個別支援計画に身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由の記載。←会議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定していくために行うものとなります。利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討することが重要となります。」
これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了承を得ることが必要となります。
様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。
必要な喜朗がされていない場合は、運営基準違反に問われる場合があります。↓
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する「身体拘束廃止未実施減算」が創設されました。
<身体拘束廃止未実施減算(新設)> 5単位/日
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
(身体拘束等の禁止)
第48条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3.座位保持装置等に付属するベルトやテープの使用
身体拘束に該当する行為とは、本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる各種の行為であると解されるため、座位保持装置等にみられるように障害者の身体状況に合わせて変形や拘縮を防止し、体幹を安定させることで活動性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断することは適当ではないため、目的に応じて適切に判断することが求められます。
ただし、座位保持装置等であっても、ベルトやテーブルをしたまま障害者を椅子の上で長時間放置するようなく甥については身体拘束に該当する場合もあるため、留意が必要です。
4.身体拘束としての行動制限について
やむを得ず行動制限をする必要があったとしても、その必要性を慎重に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければなりません。また、判断に当たっては適切な手続きを踏む必要があります。
しかし、職員の行動障害に対する知識や支援技術が十分でない場合、対応方法が分からずに行動制限をすることに頼ってしまうことも起こります。行動制限をすることが日常化してしまうと「切迫性」「非代替性」「一時性」のいずれも該当しなくなり、いつの間にか身体的虐待を続けている状態に陥っていたということにもなりかねません。職員の行動障害に対する知識や支援技術を高め、行動制限や身体拘束の解消に向けての道筋を明確にして、職員全体で支援の質の向上に取り組む必要があります。