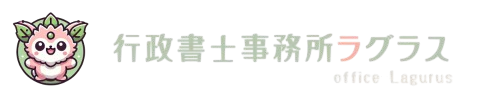就労選択支援は、令和7年10月から実施されます。
本人が就労能力や適性を客観的に評価するとともに、本人の強みや課題を明らかにし、就労に当たって必要な支援や配慮を整理し、本人と一緒に将来の働き方などを考え、必要に応じて事業者等との連絡調整を実施するものです。
就労選択支援とは
概要
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス
障害者総合支援法 第5条
13項 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適正、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう
目的
①本人の強みや課題、特徴を本人と協同して整理し、自己理解を促すこと
②その過程や結果を通じて、本人が進路を選び、決めていくこと
を支援します。
留意点「就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない」
要件
| 定員 | 10人以上 |
| 従事者 | 管理者 |
| 就労選択支援員 15:1以上 | |
| 実施主体 | ・就労移行支援事業所 ・就労継続支援事業所 ・障害者就業・生活支援センター事業の受託法人 ・自治体設置の就労支援センター ・障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関 |
実施主体:指定基準において「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定めている
就労選択支援員
要件
就労選択支援員養成研修を修了していること
令和9年度末までの経過措置
下記の研修のうち、いずれかの研修修了者は就労選択支援員養成研修の受講可能
- 障害者の就労支援に関する基礎的研修
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修コース別研修(就労支援コース)
就労選択支援員養成研修
目的
就労を希望する障害者が、就労先や働き方をより適切に検討・選択し、障害特性を踏まえたサービスの提供や就労を通じた知識・能力の発揮・向上につなげられるためには、就労選択支援に従事する就労選択支援員は専門的知見を習得している必要がある。
就労選択支援を円滑に開始し、実効性あるサービスとするため、就労選択支援員養成研修が広く周知・理解されるようになることを目的として実施
受講対象者
基礎的研修を修了していること、または「障害者の就労支援分野の勤務実績」が通算5年以上あること。
※経過措置
研修受講の流れ
- 1研修申し込み
- 2受講可否通知
- 3動画視聴(オンデマンド講義)
- 4対面演習受講
- 5アンケート回答
- 6終了証発行
対象者
- 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
- 就労継続支援B型―就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者→新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合、就労選択支援をあらかじめ利用する
- 50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になっている者等―就労アセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用可
- 就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用可
- 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等
- 近隣に就労選択支援事業所がない場合
- 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合