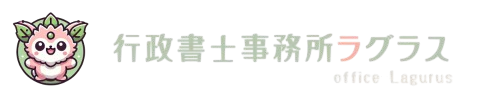判断能力が不十分な方への支援制度
精神障害、知的障害、認知症などの理由により判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。
高齢者だけの制度ではありません。精神障害(知的障害含む)は障害により意思決定に支障が生じることがあります。親族のいないご本人様。お子様が障害をお持ちの方。支援のうちの一つです。

法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度―判断能力が不十分になってしまった後に、周囲の方などが申し立てを行って家庭裁判所が後見人を選定する制度です。家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見を選任します。権限も基本的に法律で定められています。
任意後見制度―精神上の障害(認知症、精神障害、知的障害など)で、将来自身の判断能力が不十分となった後に、本人に代わってしてもらいたいことを備えるための制度です。
任意後見契約が登記されている場合において、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
→判断能力が不十分になる前に任意後見制度
判断能力が不十分になってから法定後見制度
<法定後見制度の流れ>
| 法定後見制度 | |||
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
| 対象となる方 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力を欠く常況にある方 |
| 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 民法13条1項のほか、申し立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
| 成年後見人等が代理することができる行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
準備(注意事項の確認)
注意事項
・手続きの途中での取り下げはできません。家庭裁判所の許可が必要になります。
・親族などを後見人等候補者に記載しても選ばれるとは限りません。
・原則として、後見人等はご本人がお亡くなりになるまで続きます。
裁判所へ連絡(予約をとる)
申込書の提出の前に調査官との面談の予約を取ります。
管轄の家庭裁判所へ電話をします。
書類の郵送
申立関係の書類一式を裁判所に郵送します。
(一式をコピーをとっておきます)
面談
申立人―「申立事情説明書」に基づき、生活状況、親族らの意向等について
後見人等候補者―「後見人等候補者事情説明書」に基づき、欠格事由の有無、適当かどうか
持ち物―申立書のコピー、印鑑(申立書に押印したもの)、身分証
本人面談
直接本人に意見を聞く場を設けられる場合があります。
保佐、補助の場合は必ず行われます。
親族の意向の調査
ご本人に、成年後見人等、後見人等が選任されることについて同意するかの確認になります。
申立時に同意書を提出されている場合は行われません。
鑑定
裁判所がご本人に対し、鑑定が必要だと判断した場合に医師による鑑定が行われます。
審判
裁判所が総合的に判断したのち、後見等開始の審判をし、後見人等を選任します。
審判書の送付
審判がなされると、審判書謄本が送付されます。
不服がある場合は、審判所謄本が届いてから2週間以内に行います。
職務開始
審判が確定すると、後見人等の職務を開始し、同時に審判の内容が登記されます。
<任意後見制度の流れ>
申し立て
申立人:ご本人(任意後見契約のご本人)
配偶者
四親等内の親族
任意後見受任者
書類:申立書
ご本人の戸籍謄本
任意後見契約公正証書の写し
成年後見等に関する登記事項証明書
診断書
財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
報告
成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、ご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出。
成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を求めます。
ご本人の住所地の家庭裁判所へ
事情を尋ねられる場合があります
審判
後見開始の審判と、成年後見人等の選任
報告
成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、ご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出。
成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を求めます。
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
民法9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認められる認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する制度です。
※法定成年後見の申立ての代理や代行を行うことはできませんが、成年後見制度に関するサポートを行うことは可能です。