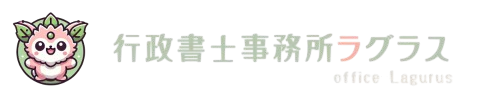就労アセスメント(就労継続支援B型)
就労アセスメントとは
主に就労継続支援B型事業所の利用希望者に対して実施され、就労能力を評価するアセスメントの一つ。具体的な作業などを通し、さまざまな側面から評価を行い評価します。
事業所利用開始前、利用中、求職段階、企業就労への移行段階など適宜行います。
このアセスメントをもとに個別支援計画を作成することになります。
障害者の就労支援とアセスメント
就労アセスメントの基本的考え方
「働く力」と「生活の力」は平衡はしません。就労アセスメントは一般就労の可能性を、一定の基準を設けて「判定」するものではありません。
地域で働くためには、生活面が安定することが重要と考えられ、将来、相談支援事業所など支援機関と連携しながら利用者が働き・暮らすことをイメージしてアセスメントを行う必要があります。
就労アセスメントにおけるそれぞれの役割
| 管理者 (全体の調整者) | ・就労アセスメントにかかる管理・統括 ・就労アセスメントの実施に係る全体的な連絡調整・総括 |
| サービス管理責任者 | ・各担当者の業務分担の調整 ・就労アセスメントのための「個別支援計画」の作成 |
| 生活支援員 | ・自施設内における利用者の生活面のアセスメントの実施・記録 ・家族や特別支援学校教諭等からの聞き取りや総合記録票による普段の生活面のアセスメントの実施 |
| 職業指導員 | ・自施設内における利用者の作業場面の観察等による作業面のアセスメントの実施・記録 ・作業日誌の記録 |
| 就労支援員 | ・家族や特別支援学校等からの聞き取りや作業面のアセスメントの実施 ・一般就労や一般就労を支える支援内容の情報提供 ・進路希望の把握 ・就労アセスメントの実施の際に施設外支援を行う場合は、実習先(企業等)への連絡や調整 |
| その他 (各職員で役割分担する項目) | ・最終的な就労アセスメント結果を検討する際の資料(総合記録票・アセスメント結果票)の作成 |
使用する資料(例)
総合記録表
利用者の進路希望や普段(家庭や利用者が所属する機関(特別支援学校等))の様子等を事前に確認する目的や、アセスメント期間中に把握された利用者のアセスメント結果を記録する目的。
就労アセスメント結果票
利用者の情報を整理し、利用者や保護者へのアセスメントの結果を報告するとき、各支援機関において情報共有のために活用。
作業日誌
アセスメント期間中、利用者や保護者との連絡を円滑にし、一日のアセスメントが終了した後の家庭での利用者の様子を把握することもできる。
利用者が就労移行支援事業所で行った作業や周囲の環境に対してどのような感想を持っているか、疲労や健康の度合いによる変化の有無、利用者や保護者がどのような認識でアセスメントに臨み、どのように自己評価しているか等を把握するために活用。
就労アセスメントのための作業課題
利用者が期間中に取り組む作業課題を設定する。
実施手順とポイント
期間設定
就労アセスメントの標準実施期間は約1か月間です。
複数の作業を経験した上での比較や、時間の経過による変化の観察、面談等を行い、利用者の就労能力の伸び(成長力)、長所や課題を把握します。
アセスメントの三段階
利用者が取り組みやすい作業から開始することが望ましいと考えられます。
- アセスメントを実施する際―利用者の所属する機関(特別支援学校等)に事前に創造記録票に記入を依頼し、把握した内容と作業能力確認①における簡易作業の様子に相違があるかを比較かんさつする
- 利用者の緊張感が高い場合―利用者の理解度や緊張度に合わせた課題設定ができる簡易な作業を課題として設定する
- 利用者と一緒に会話をしながら作業を進め、信頼関係の形成につなげる
慣れない環境でスタートすることが想定されるため、就労移行支援事業所での規則・習慣に沿った生活を送ることができるように、事業所全体でサポートしながらアセスメントを実施します。
アセスメント期間であることを意識しすぎて利用者から遠く離れて観察するのではなく、利用者の緊張を和らげるように関わっていくことが重要です。
障害特性等により、新しい環境に慣れるまでに時間がかかったり、緊張感の強さからスタート時点でつまずいてしまったりすることも少なくないため、保護者や利用者の所属する機関とも連絡を取り、サポートとアセスメントを並行して実施していくことが望まれます。
<作業能力確認②> 留意点
- 一人の支援員だけでは利用者の作業手順の理解、作業への集中、作業速度の向上が図れないこともある―利用者のコミュニケーション能力に応じて伝わりやすい方法は何かを検討する等、事業所全体で支援効果を上げていく必要があります
- 保護者や利用者の所属する機関と連絡を取ることにより、利用者自身にとって良い結果が得られるための支援方法について助言や情報を得ることも重要です
- アセスメントが作業の観察だけになり、「できた」「できなかった」だけのアセスメントになってしまっては不十分です。観察結果をもとに利用者ごとの課題に対して、アプローチを行ったうえで、利用者の反応も含めてアセスメントする必要があります。
導入期<面談> 留意点
生活面の課題が把握された場合、保護者や利用者が所属する機関と連絡を取り、利用者への支援方法について、助言を得ることが重要です。
アセスメント期間内では十分な改善効果が見られない場合であっても、期間中に見られた課題を保護者や特別支援学校、相談支援事業所、進路先等と情報共有することも有効と考えられます。
利用者と関わった支援員やサービス管理責任者等が、それぞれの視点から観察した利用者に関する情報を共有し、総合的に取りまとめます。
第1週目のアセスメント項目を継続して観察していくとともに、利用者が就労移行支援事業所内において環境に「慣れ」を感じる時期であるため、「慣れ」による変化がどのように現れるかを考慮して観察することが重要です。
時間の経過とともに作業の力や姿勢に変化はないか、周囲との対人関係がどのような様子かを観察する時期となります。
第1週目の面談時に把握した日常生活や余暇活動等の情報について大きな変化がないかを確認しつつ、1週目に何か課題があった場合に行った支援の効果について確認します。
作業遂行能力の向上や労働習慣の確立が図られているかを観察します。
<作業能力確認>④ 留意点
これまでに支援した事項が、「どこまで習慣化、確率化されたか」、あるいは「されつつあるか」を把握して、利用者や周囲の状況がどのように変化しているか、更に支援が必要となる項目の有無の確認と、今後の成長の可能性についても把握します。
さらに「集団作業」や「流れ作業」などにおいて、時間の経過による緊張感の緩和や環境への慣れ等によって生み出された人間関係や、逆に周囲との協調を阻害する要因等の発見と、要因除去の可能性についても注意深くアセスメントすることが大切です。
この段階のアセスメント結果は、利用者が将来職場や進路先で発生する就労上の課題や支援ポイントと直結する結果であることが多いため、アセスメント時に利用者の小さな変化を見逃さないように留意して記録を残すようにします。
利用者がこれまでに体得した基本的な職業生活能力を全体的に評価する最終的な段階です。企業で職場実習を行うことで、より実践的なアセスメントを行うことができます。
<企業等実習> 留意点
利用者にとっては、最も実践的なアセスメントを行う時期となり、ストレスの度合いも大きくなりますので、評価者は利用者の精神的状態を把握しながらアセスメントを進めてください。
企業の作業内容によっては、利用者が十分に取り組めない場合も想定されます。必要に応じて、企業と調整し、作業課題を変更していただく、要求水準を緩和していただくなどにより、利用者に過度な負担にならないよう心がけます。
これらを可能とするためには、事前に総合記録票で把握した結果や、アセスメント期間中の様子を基に、利用者の障害特性や健康状況を事前に十分把握しておく等、事前の準備や周囲との打ち合わせや調整を行っておくことが重要です。
利用者が自然な姿で取り組んでいる様子が観察できるように、徐々に単独で作業に取り組む時間を増やしていくことにも心がけます。
職場実習が困難な場合は、できる限り企業の作業場面に近い環境を設定して、企業実習と同様の経験を利用者が行えるよう留意します。
※<企業等実習>での利用者への聞き取り
評価者は、利用者に対して、就労アセスメントを経験してみての感想や、就労アセスメント開始時に希望していた就労系障害福祉サービスの利用について、現在はどのような考え(ニーズ)を持っているのか等を捉えていくことが望ましいと思われます。
利用者や保護者等から、アセスメント終了後に希望する事業を利用できるかについて、相談があることも相談されますが、将来の一般就労への移行の可能性を見出したり、各支援機関が行う就労支援に活用するためにアセスメントを実施していることを確認します。
<企業等実習>のとりまとめ 留意点
<企業等実習>期間中は企業的な視点に立ち、利用者がどの程度自立して作業を遂行できるかを把握します。
実習先の企業に訪問した際には、利用者を観察するだけでなく、企業の担当者や可能であれば周囲の従業員からも利用者の状況や評価を確認するように心がけます。
<企業等実習>は、アセスメントの最終段階にあることから、このアセスメントの経験によって、今後の進路に関する希望や意見に変化があったか、保護者にも連絡を取り、<事業所内評価会議>の実施前段階で把握しておくことが必要です。
※<企業等実習>の終了後の記録の整理
企業等実習を終了した時点で、評価者は必ず今までのアセスメント結果を取りまとめ、各段階ごとの支援の効果や時間経過による変化等について振り返り、把握しておくことが必要です。
重点的な支援内容及びその結果、利用者の特徴的な行動や事象、各評価項目の評価結果等について、整理します。
評価者が単独で判断せず、就労移行支援事業所全体で取りまとめることが望ましいと考えられます。
利用者への支援を行うにあたって、それぞれが共通認識を持つことが重要であるため、利用者や保護者に加えて、各支援機関が可能な範囲で参加することが重要です。
―厚生労働省「就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」より