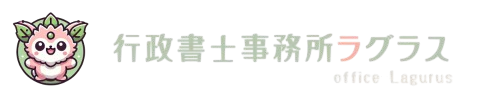障害者虐待防止法の概要
1.「障害者虐待」の定義
障害者の定義
障害者虐待防止法では、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義されています。
「身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」
障害者手帳を取得していない場合も含まれます。また18歳未満の者も含まれます。
障害者基本法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
「障害者虐待」に該当する場合
障害者虐待防止法第2条第2項では、「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」による虐待を特に「障害者虐待」と定めています。
養護者―障碍者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人
使用者―障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働に関する事項について事業主のために行為をする者
「障害者福祉施設従事者等」―障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(定義)
第二条
2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
2.障害福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者虐待防止法第2条第7項では、これらの事業に従事する人たちが、次の行為を行った場合を「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待といいます。
①身体的虐待
②性的虐待
③心理的虐待
④放棄・放置
⑤経済的虐待
高齢者関係の施設の入所者に対する虐待については、65歳未満の障害者に対する者も含める―高齢者虐待防止法
18歳以上で、障害者総合支援法による給付を受けながら児童福祉施設に入所している者―障害者虐待防止法
虐待の種類 | 内容 | 刑事罰 |
|---|---|---|
| 身体的虐待 | 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること | 第199条 殺人罪、第204条 傷害罪、第208条 暴行罪、第220条 逮捕監禁罪 |
| 性的虐待 | 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること | 第176条 強制わいせつ罪、第177条 強制性交等罪、第178条 準強制わいせつ罪、準強制性交等罪 |
| 心理的虐待 | 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと | 第222条 脅迫罪、第223条 強要罪、第230条 名誉棄損罪、第231条 侮辱罪 |
| 放棄・放置 | 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による上記3つまでに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること | 第218条 保護責任者遺棄罪 |
| 経済的虐待 | 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること | 第235条 窃盗罪、第246条 詐欺罪、第249条 恐喝罪、第252条 横領罪 |
7 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。
一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
3.障害者福祉施設等の虐待防止と対応
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に通報する義務があります。(障害者虐待防止法第16条)
明らかに虐待を受けた場面を目撃した場合だけでなく、虐待を受けたのではないかと疑いを持った場合は、事実が確認できなくても通報する義務があります。また、相談を受けた管理者等も市町村に通報する義務が生じます。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等)
第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
4 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則
市町村・都道府県が職務権限で立ち入り調査を行った場合に、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を行った者を30万円以下の罰金に処することができます。(障害者総合支援法第110条、第111条)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第百十条 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十一条 第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の三十二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解
法人の理事長、障害者福祉施設等の管理者には、障害者福祉施設等が障害者の人権を擁護する拠点であるという高い意識と、そのための風通しの良い開かれた運営姿勢、職員と共に質の高い支援に取り組む体制づくりが求められます。
障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、職員の研修の実施、利用者やその家族からの苦情解決のための体制整備、その他の障害者虐待の防止のための措置を講じること。(障害者虐待防止法第15条)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置)
第十五条 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。
4.虐待を防止するための体制
運営規定への定めと職員への周知
指定障害者支援施設等の一般原則
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、その従事者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない
職員に会議等機会あるごとに支援方針を確認し浸透させ、徹底させることが必要です。
また、職員に対してだけでなく、利用者の家族、外部の見学者等に対しても、重要事項説明書や障害者福祉施設等のパンフレットへの記載を通じて周知することが必要です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準について
虐待の防止のための措置に関する事項(第8号)
居宅介護における「虐待の防止のための措置」については、「障害者(児)施設における虐待の防止について」に準じた取り扱いをすることとし、指定居宅介護事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られるための必要な措置について、あらかじめ運営規定に定めることとしたものである。具体的には、
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画等)を指すものであること
虐待防止委員会を設置する等の体制整備
| 虐待防止委員会 | 委員長:管理者 委員:虐待防止マネジャー 看護師・事務長 利用者や家族の代表者 苦情解決第三者委員 など | ・研修計画の策定 ・職員のストレスマネジメント・苦情解決 ・チェックリストの集計、分析と防止の取組検討 ・事故対応の総括 ・他の施設との連携 等 |
| 虐待防止マネジャー | 各部署の責任者 サービス管理責任者など | ・各職員のチェックリストの実施 ・倫理綱領等の浸透、研修の実施 ・ひやり・ハット事例の報告、分析等 |
虐待防止委員会の役割
倫理綱領・行動指針・掲示物等の周知徹底
虐待を許さないための「倫理綱領」「行動指針」等の策定、「虐待防止マニュアル」に作成、「権利侵害防止の掲示物」の掲示等により職員に周知徹底を図る必要があります。