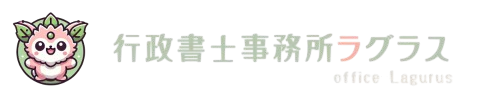5.人権意識、知識や技術向上のための研修
研修の種類(例)
虐待防止法で障害者虐待防止の責務を規定されている障害者福祉施設等設置者、管理者等に対する研修は極めて重要です。
・基本的な職業倫理
・倫理綱領、行動指針、掲示物の周知
・障害者虐待防止法等関係法律や通知、指定基準等の理解
・障害当事者や家族の思いを聞くための講演会
・過去の虐待事件の事例を知る 等
職員が職場の中で過度のストレスを抱えていたり、他の職員から孤立していることも、虐待が起きやすくなる要因のひとつと考えられるので、職員が一人で悩みや問題を抱え込んで、孤立することを防ぎ、職員同士が支えあう風通しの良い職場づくりを進めることが虐待防止につながります。
・アンガーマネジメント 等
障害者虐待に関する調査では、障害種別毎に起こりえる虐待類型に違いがあることが報告されています。また、虐待の多くが、障害特性に対する知識不足や、「問題行動」と呼ばれる行動への対応に対する技術不足の結果起きています。
・障害者や精神的な疾患等の正しい理解
・行動障害の背景、理由を理解するアセスメントの技法
・自閉症の支援手法(視覚化、構造化等)
・身体拘束、行動制限の廃止
・服薬調整
・他の障害者福祉施設等の見学や経験交流 等
個別支援計画の内容を充実強化するための研修として有効です。内部の経験・知識が豊富なスーパーバイザーや外部の専門家による助言を得て行うことで、今後の支援の方向性が拓けるなど、支援の質の向上につながります。
・障害者のニーズをくみ取るための視点の保持
・個別のニーズを実現するための社会資源等の情報や知識の習得
・個別支援計画というツールを活用しての一貫した支援及び支援者の役割分担等
障害者福祉施設の利用者や家族等に対する障害者虐待防止法の理解や早期発見のための研修を実施することも有効です。
研修を実施する上での留意点
①研修対象者への留意
職員一人ひとりの研修ニーズを把握しながら、職員の業務の遂行状況を確認しながら研修計画を立てます。関係職員(福祉職に限らず、給食調理、事務、運転、宿直管理等の業務を担う職員も支援者と言えます)に対して研修を実施することが望まれます。新任職員や短時間労働の従業者等については、理解が不十分である場合が多く、質のが高い支援を実施できるように教育する必要があります。また、ヒヤリハット事例等を集積して日々の業務を振り返る内容とする必要があります。
②職場研修(OJT)と職場外研修(off JT)の適切な組み合わせにより実施
職場外研修は、障害者福祉施設等以外の情報を得て自らを客観視する機会を持つことができ、日々の業務の振り返りができます。
③年間研修計画の作成と見直しを虐待防止委員会で定期的に行う
実施された研修の報告、伝達がどのように行われたのか、職員の自己学習はどうであったのかについても検証し、評価することが重要です。
6.虐待を防止するための取組について
(1)日常的な支援場面等の把握
管理者による現場の把握
障害者虐待を防止するためには、管理者が現場に直接足を運び支援場面の様子をよく見たり、雰囲気を感じたりして、不適切な対応が行われていないか日常的に把握しておくことが重要です。
日ごろから、利用者や職員、サービス管理責任者、現場のリーダーとのコミュニケーションを深め、日々の取組の様子を聞きながら、話の内容に不適切な対応につながりかねないエピソードが含まれていないか、職員の配置は適切か等注意を払う必要があります。また、グループホーム等地域に点在する事業所は管理者等の訪問機会も少なく、目が届きにくい場合もあるため、頻繁に巡回する等管理体制に留意する必要があります。
性的虐待防止の取組
性的虐待は、他の虐待行為よりも一層人目に付きにくい場所を選んで行われることや、被害者や家族が人に知られたくないという思いから告訴・告発に踏み切れなかったり、虐待の通報・届出を控えたりすること等の理由により、その実態が潜在化していることが考えられます。
これらの虐待は、被害に遭った利用者の情緒が急に不安定になったなど、本人の様子の変化を不審に思った家族や、虐待者である職員が異性の利用者とばかり接する等の問題行動があることに、他の職員が気づくなどが、虐待発見の端緒になっている場合があります。
・職員採用時に支援の現場に試しに入ってもらい、気になる行動がないか確認すること
・支援の現場においては勤務シフトや業務内容の分担の工夫
・同性介助ができる体制を整える
・勤務中は個人の携帯電話やスマートフォンの携行を禁止し不当な撮影を防止する 等
経済的虐待防止の取組
・預金通帳と印鑑を別々に保管する
・複数の者により適切な管理が行われていることの確認が常に行える体制で出納事務を行う
・利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等の適切な管理体制の確立
・成年後見制度の活用 等
(2)風通しの良い職場づくり
虐待が行われる背景については、密室の環境下で行われるとともに、組織の閉塞性、閉鎖性がもたらすという指摘があります。
職員は、他の職員の不適切な対応に気が付いたときは上司に相談した上で、職員同士で指摘をしたり、どうしたら不適切な対応をしなくて済むようにできるか話し合って全職員で取り組めるようにしたりする等、オープンな虐待防止対応を心がけ、職員のモチベーション及び支援の質の向上につなげることが大切です。
・支援に当たっての悩みや苦労を職員が日ごろから相談できる体制
・職員の小さな気づきも職員が組織内でオープンに意見交換し情報共有する体制
・職員のストレス軽減のため、夜間の人員配置等を含め、管理者は職場の状況を把握する
(3)虐待防止のための具体的な環境整備
事故・ヒヤリハット事例の報告
ヒヤリハット事例が見過ごされ、誰からも指摘を受けず気づかずに放置されることは、虐待や不適切な支援、事故につながります。早い段階で事例を把握・分析し、適切な対策を講じることが必要です。
| 分析と検討のポイント | |
|---|---|
| 情報収集 | 提出されたヒヤリハット事例報告書や、施設長会議等を活用して、他の施設における同様の事故情報等を収集する等、事故発生の状況要因等を洗い出す |
| 原因解明 | 問題点を明確にし、評価・分析する |
| 対策の策定 | 虐待防止委員会等において、防止策を検討する |
| 周知徹底 | 決定した防止策等を各部署に伝達し、実行する |
| 再評価 | 防止策の効果が表れない場合、再度、防止策を検討する |
虐待防止チェックリストの活用
管理者の立場、職員の立場それぞれによる複眼的なチェックリストを作成します。
| 管理者 | ・運営規定の整備 ・職員の理解 ・研修計画 ・利用者や家族との連携 ・外部との関係 ・体制の整備 等 |
| 職員 | 利用者への支援の適否等 |
計画→実行→確認→対応処置を繰り返します
苦情への適切な対応は、利用者の満足感を高めること等に加え、虐待防止対策のツールのひとつでもあります。
そのため、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員を設置し、連絡等を障害者福祉施設等内に掲示する他、障害者福祉施設等の会報誌に掲載する等、積極的に周知を図ることが必要となります。
利用者の家族に対しても、苦情相談の窓口や虐待の通報先について周知するとともに、日ごろから話しやすい雰囲気をもって接し、施設の対応について疑問や苦情が寄せられた場合は話を傾聴し、事実を確認することが虐待の早期発見につながります。
施設等への遠慮から、直接苦情を言いにくい人もいるので、市町村障害者虐待防止センターや相談支援事業所に相談することや、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会等の苦情解決制度についても積極的に周知する必要があります。
チェックリストの作成と評価は自己評価なので、これに加えて外部による第三者評価を受けることもサービスの質の向上を図るきっかけとして有効になります。
障害福祉サービスの申請または変更の際に、サービス等利用計画案の提出が必要となり、サービス等利用計画が適切であるかどうかについて、サービスの利用状況を検証し、必要に応じてサービス等利用計画を見直すために、定期的に相談支援専門員がモニタリングを実施しますので、サービスの実施状況を確認する重要な機会となります。
多くの目で利用者を見守るような環境作りが大切です。管理者はボランティアや実習生の受入れ体制を整え、積極的に第三者が出入りできる環境づくりを進め、施設に対する感想や意見を聞くことにより、虐待の芽に気づき、予防する機会が増えることにもつながります。
その人に必要な諸制度の活用を検討し支援することが求められます。
成年後見制度の活用等―自ら権利を擁護することに困難を抱える障害者について権利擁護を行っています。
日常生活自立支援事業―判断能力が十分でない人が地域で自立して生活ができるように、福祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理を行っています。