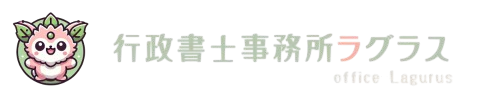7.(自立支援)協議会等を通じた地域の連携
障害者虐待の防止や早期の対応等を図るためには、市町村や都道府県が中心となって、関係機関との連携協力体制を構築しておくことが大切です。
地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、身体障害者相談員、知的障害者相談員、家族会等からなる地域の見守りネットワーク
養護者による障害者虐待事案等において、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者等虐待が発生した場合に素早く具体的な支援を行っていくためのネットワーク
警察、弁護士、精神科を含む医療機関、社会福祉士、権利擁護団体等専門知識等を要する場合に援助を求めるためのネットワーク
虐待場疑われる事案があった場合の対応
1.虐待が疑われる事案があった場合の対応
障害者虐待防止法第16条に規定されている通報義務に基づき、虐待を受けた利用者の支給決定をした市町村の窓口に通報します。(通報せず、施設の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することとなります)
内部的には法人の理事長に報告し、必要に応じて臨時理事会の開催について検討します。
2.通報者の保護
通報した職員は、障害者虐待防止法で次のように保護されます。
- 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をしたことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いを受けないこと(通報が虚偽であるもの及び一般人であれば虐待であったと考えることに合理性がない「過失」による場合は除く)
3.市町村・都道府県による事実確認への協力
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報・届出があったときは、市町村及び都道府県が、事実を確認するために障害者やその家族、障害者福祉施設等関係者からの聞き取りや、障害者総合支援法や社会福祉法等の関係法令に基づく調査等を速やかに開始することとなります。
そのため、調査に当たっては、聞き取りを受ける障害者やその家族、障害者福祉施設等関係者の話の秘密が守られ、安心して話せる場所の設定が必要となりますので、適切な場所を提供します。また、勤務表や個別支援計画、介護記録等の提出が求められますので、これらに最大限協力します。(虚偽の答弁をしたり、検査を妨害した場合は罰せられることがあります)
4.虐待を受けた障害者や家族への対応
虐待事案への対応に当たっては、虐待を受けた利用者の安全確保を最優先にします。
→虐待を行った職員の配属先の変更や、事実関係が明らかになるまでの間、出勤停止にする等の対応を行い、利用者が安心できる環境づくりに努めます。
事実確認をしっかりと行ったうえで、虐待を受けた障害者やその家族に対して障害者福祉施設等内で起きた事態に対して謝罪も含めて誠意ある対応を行います。
5.原因の分析と再発の防止

虐待防止委員会だけでなく、第三者的立場の有識者にも参加してもい検証委員会を立ち上げること等も考えられます。
虐待が起きると、施設は利用者や家族からの信頼を失うとともに、社会的な信用が低下し、虐待に関わっていなかった職員も自信を失ってしまいます。失ったものを回復するためには、事実の解明や改善に向けた誠実な取組と長い時間が必要になります。虐待が起きてしまった原因を明らかにし、どうしたら虐待を防ぐことができたのかを振り返るとともに、行政の改善指導等に従い、今後の再発防止に向けた改善計画を具体化した上で、同じ誤りを繰り返すことがないように取り組むことが支援の質を向上させるだけではなく、職員が自信を取り戻し、施設が利用者や家族からの信頼を回復することにもつながります。
6.虐待した職員や役職者への処分等
事実の確認と原因の分析を通じて虐待に関係した職員や施設の役職者の責任を明らかにする必要があります。刑事責任や民事責任、行政責任に加え、道義的責任が問われる場合がありますので、真摯に受け止めなくてはなりません。
さらに、法人として責任の所在に応じた処分を行うことになります。
- 法人-労働関連法規及び就業規則の規定等に基づく
- 処分を受けた者―虐待防止、職業倫理等に関する教育や研修の受講を義務付ける等、再発防止のための対応
市町村・都道府県による障害者福祉施設等への指導等
1.市町村・都道府県による事実確認と権限の行使
障害者虐待が疑われる障害者福祉施設
市町村・都道府県
虐待が認められた場合―改善指導等(虐待防止計画の作成、第三者による虐待防止のための委員会の設置、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェック 等)
指導に従わない場合―勧告・命令、指定の取消等の処分
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(通報等を受けた場合の措置)
第十九条 市町村が第十六条第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届出を受け、又は都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、障害者福祉施設の業務又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る障害者に対する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。
2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況の公表
公表制度の趣旨
各都道府県において、障害祝詞施設従事者等による障害者虐待の状況を定期的かつ的確に把握し、各都道府県における障害者虐待の防止に向けた取組に反映していくことをもくてきとするものであり、公表することによりこれらの施設等に対して制裁を与えることを目的とするものではありません。
(公表)
第二十条 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。