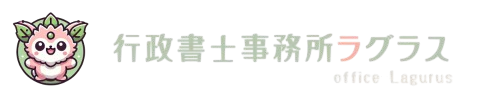障害者支援制度のひとつに「訪問看護」があります。
ご自宅で障害に応じた看護をしてもらえます。
主治医から「訪問看護指示書」を交付を受ける必要があるので、相談してみましょう。
訪問看護とは
概要
病気や障害により継続して自宅で療養している方に対し、自宅に看護師などが訪問して療養上のお世話や医療的ケアを行います。
目的
- 悪化防止
- 心身の機能維持
- 生活の質の向上
- 自宅で最期を迎えたい方のための看取り
対象者
| ① | 介護保険 | 1号被保険者 | 65歳以上の方で、要支援・要介護と認定された方 |
| 2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の方で16特定疾病疾患の対象者で要支援・要介護と認定された方 | ||
| ② | 医療保険 | 40歳未満の方 | |
| 40歳以上65歳未満の方 | ・16特定疾病の対象でない方 ・要支援、要介護に該当しない方 ・介護保険を利用しない方 | ||
| ③ | 重症心身障害者(児) | ||
- ①について:介護保険が優先だが、以下の方は医療保険
- 厚生労働大臣が定める疾病等
- 精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)
- 病状の悪化等により特別訪問看護指示機関にある方
内容
- 療養生活支援
- 食事、排せつ、入浴、先発などの介助。
- 清潔保持など
- 療養生活相談
- 病状や健康状態の管理と看護
- 医療処置・治療上の看護
- 点滴、注射、褥瘡の処置
- カテーテル管理など
- 認知症の人の看護
- 精神障がい者の看護
- リハビリテーション
- 理学療法士や作業療法士などによる、機能回復や生活訓練などのサポート
- 苦痛の緩和と看護
- 家族の相談、支援
- 住まいの療養環境の調整、支援
- 地域の社会資源の活用
- エンドオブライフケア(病気や老いによって人生の終焉を迎える時期に、人が最期までその人らしく生きられるよう支援するケア)
- 在宅移行支援(外泊中の訪問看護等)
精神科訪問看護
内容
- 日常生活の維持
- 生活技能の獲得・拡大、食生活、活動、安全確保、などのモニタリングと技能の維持向上のためのケア
- 服薬管理やセルフケアの援助
- 精神症状の悪化や憎悪を防ぐ
- 症状のモニタリング
- 症状安定・改善のためのケア
- 服薬・通院継続のための関わり
- 症状のモニタリング
- 身体症状の悪化や進行を防ぐ
- 身体症状のモニタリング、バイタル測定
- 生活習慣に関する助言・指導
- 自己管理能力を高める援助
- 社会復帰支援
- 対人関係の維持・構築
- コミュニケーション能力の維持向上の援助
- 他者との関係性への援助
- ご家族のサポート
- 家族関係の調整、家族との関係性に関する援助
- 家族に対する援助
- 各種医療職種との連携サポート
- ケアの連携施設内外の関連職種との連携・ネットワーキング
- 社会資源の活用・情報提供、利用のための援助
- エンパワーメント(人々が本来持っている力や能力を発揮し、自立的に行動できる状態を支援すること)
- 自己効力感を高める
- コントロール間を高める
- 肯定的フィードバック
対象者
ICD(世界保健機関)が提唱する精神および行動の障害の分類(F00~F99)のすべてになります。
利用にあたり
- 精神科担当の医師による指示書が必要
- サービスを提供できるのは、精神科訪問看護を実施する施設