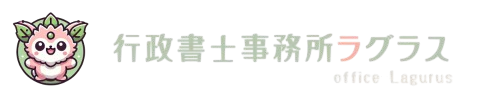障害児入所施設とは
- 平成24年度からそれまで各障害別に分かれていた障害児の入所施設が「障害児入所施設」として一元化しました。
- ①福祉型障害児入所施設と②医療型障害児入所施設の2類型があります。
- 重度・重複障害や被虐待児への対応を図るほか、自立(地域生活移行)のための支援を充実
目的・基本理念・原理
- 障害のある児童を入所させ、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識、技能の付与を行う
- 障害児支援においては子どもの発達における幅が大きいこと、個人差があることなどを踏まえ、これに応じた養育や支援を提供する
- 不安の解消と安定や発達の豊かさにつなげていく
- 「児童の権利に関する条約」を踏まえ、特に障害児については第2条、第3条、第12条、第23条が重要
- 「障害者の権利に関する条約」では7条
- 「児童福祉法」では2条
| 児童の権利に関する条約 | |
| 2条 | 児童およびその父母・保護者・家族の構成員に対する差別禁止。 人種・皮膚の色・言語、性別、宗教・思想信条、社会的身分や財産、心身障害などによる差別的取り扱いを禁ずる。 |
| 3条 | 児童の最善の利益の保護。 締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める。 |
| 12条 | 児童の意見表明権。 児童は自らに影響を及ぼすすべての事項について、自由に自己の意見(原文:views、考察・考え)を表明する権利を有する。 自らに影響を及ぼす司法上・行政上の手続において、国内法の手続規則にのっとり聴取される機会を与えられる。 |
| 23条 | 精神的・身体的障害を有する児童の尊厳、自立促進と社会参加、医療・教育などの確保。 |
障害者の権利に関する条約 7条
障害のある子ども
締約国は、障害のある子どもが複合的な差別を受けていることを認め適当な立法的、行政的措置をとる。
児童福祉法 2条
全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
入所対象
身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
*医療型は、入所等する障害児のうち知的障碍児、肢体不自由児、重症心身障害児
*手帳の有無は問わない。児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
*3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援も可能
22歳までの入所継続が可能―一定年齢以上の入所で移行可能な状態に至っていない場合や、22歳満了時(入所の時期として最も遅い18歳直前から起算して5年間の期間)までの入所継続可能
提供するサービス
- 福祉型障害児入所施設
- 保護、日常生活の指導、知識技能の付与
- 医療型障害児入所施設
- 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
- 障害に応じて
人員基準
| 職種 | 知的障害 | 自閉症 | 盲ろうあ | 肢体不自由児 |
| 嘱託医 | 1人以上(精神科(知的障障害施設・第2種自閉症児施設)、眼科又は耳鼻咽喉科(盲ろうあ児施設)の診療に担当の経験を有する者(最低基準)) | |||
| 医師 | 1人以上 | |||
| 児童指導員及び保育士 | 総数 ①知的障害児(自閉症含む)4.3:1以上 ②盲ろうあ児 乳幼児4:1以上、少年5:1以上 ③肢体不自由児3.5:1以上 児童指導員1人以上 保育士1人以上 (30人以下を入所させる施設で知的障害児を受け入れる場合、35人以下を入所させる施設で盲ろうあ児を受け入れる場合は、さらに1人以上を加える) | |||
| 看護師 | 20:1以上 | 1人以上 | ||
| 栄養士 | 1人以上(40人以下の施設にあっては栄養士を置かないことができる) | |||
| 調理員 | 1人以上(調理業務の全部を嘱託する施設にあっては調理員を置かないことができる) | |||
| 職業指導員 | 職業指導を行う場合 | |||
| 心理指導担当職員 | 心理指導を行う場合(心理指導を行う必要があると認められる児童5人以上) | |||
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | |||
*主たる障害以外への障害を受けいれた場合には、適切な支援が提供できるよう該当する障害の人員基準等を適用する。
設備基準
| 設備 | 知的障害 | 自閉症 | 盲ろうあ | 肢体不自由 |
| 居室 | ・定員4人以下(乳幼児6人以下) ・障害児1人当たりの床面積 4.95㎡以上(乳幼児 3.3㎡) ・障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること | |||
| その他 | 調理室、浴室、便所 医務室(主たる対象の障害が知的障害、盲ろうあであって、30人未満の施設においては、設けないことができる) 静養室(主たる対象の障害が盲ろうあであって、30人未満の施設においては、設けないことができる | |||
| ・主たる対象の障害が、 知的障害及び盲ろうあ―障害児の年齢、適当に応じ職業指導に必要な設備 盲ろうあ―遊戯室、訓練室 盲―音楽設備、特殊表示等身体機能の不自由を助ける設備 肢体不自由―訓練室、屋外訓練場、身体機能の不自由を助ける設備 を備える | ||||