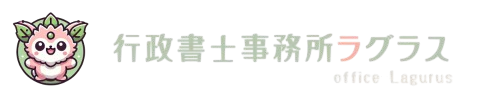ショートステイとは
居宅で介護を行っている方が病気や冠婚葬祭などで介護を行うことができない場合、障害のある方に施設に短期間入所してもらうこと。
緊急一時保護、家族のレスパイト(休息)、自立生活に向けた事前準備、本人の地域生活疲れや健康管理や維持のため、などの側面があります。
障害者総合支援法 第5条
8項 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
ショートステイ・福祉型
事業形態
利用者
- 障害支援区分「1」以上である障害者・
- 市町村が利用を認めた障害児
人員基準
| 管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(支障がなければ兼務可) | ||
| 併設型 | 従業者 | 指定障害者支援施設等 | 当該施設の利用者と短期入所の利用者の合計数を当該施設の利用者とみなし、当該施設に必要とされる数以上 |
| 空床利用型 | |||
| 指定宿泊型自立訓練事業所等 | ①又は②に掲げる指定短期入所を提供時間帯に応じ、それぞれ①又は②に定める数 ①短期入所と宿泊自立訓練等を提供する時間帯:両方の利用者の数の合計数を当該宿泊型自立訓練事業所等における利用者数とみなし、当該宿泊自立訓練等の生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる以上 ②短期入所を提供する時間帯(①を除く):当該日の短期入所の利用者数が6名以下については1以上、7名以上については利用者の数が6を超えて6又はその端数を増やすごとに1を加えて得た数以上 | ||
| 単独型 | 指定生活介護事業所等 | ①指定生活介護等のサービス提供時間帯:両方の利用者の数の合計数を当該生活介護事業所等における利用者数とみなし、当該生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる以上 ②それ以外の時間帯:当該日の短期入所の利用者数が6名以下については1以上、7名以上については利用者の数が6を超えて6又はその端数を増やすごとに1を加えて得た数以上 | |
| 指定生活介護事業所等以外 | 上記②と同じ |
指定障害者支援施設
指定障害者支援施設、児童福祉施設その他の入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる入所施設
指定宿泊型自立訓練事業所等
指定障害者支援施設等以外の必要な支援を適切に行うことができる施設。指定宿泊型自立訓練事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所
指定生活介護
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に図る(指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定宿泊型自立訓練事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型・B型事業所、指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は障害児通所支援事業所
設備基準
| 居室 | 併設型 | 併設事業所又は指定障害者支援施設等の居室であって、その全部または一部が利用者に利用されていない居室を用いる | |
| 空床利用型 | |||
| 単独型 | ・1の居室の定員:4人以下 ・地階に設けてはならない ・利用者1人当たりの床面積:収納設備等を除き8㎡以上 ・寝台又はこれに代わる設備を備える ・ブザー又はこれに代わる設備を設ける | ||
| 設備 | 併設型 | 正接事業所又は併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く)を短期入所事業の用に供することができる | |
| 空床型 | 指定障害者支援施設等とて必要とされる設備を有することで足りる | ||
| 単独型 | 食堂 | ・食事の提供に支障がない広さを有する ・必要な備品を備える | |
| 浴室 | 利用者の特性に応じたものであること | ||
| 洗面所・便所 | ・居室のある階ごとに設ける ・利用者の特性に応じたもの | ||
医療型
福祉型短期入所では、高度な医療に対応できていないため、医療機関等での短期入所であれば医療が必要な障害者(児)であっても対応できます
利用者
- 市町村から支給決定された医療的ケア児・者、重症心身障害児・者
- 進行性筋萎縮症の方
- 気管切開を伴う人工呼吸器をつけている方
- 重症心身障害児・者
- 遷延性意識障害のある方
- 筋萎縮性側索硬化症の方
人員基準・設備基準
| 併設型 | 空床利用型 | ||
| 人員基準 | 管理者 | 専ら事業所の管理業務に従事(支障がないときは他の職務との兼務可) | |
| 従業者 | 利用者を、本体施設の利用者とみなしたうえ、本体施設として必要とされる数以上 | ||
| 設備基準 | 本体施設の設備を利用することにより、ショートステイの効率的な運営が図られ、両者のサービス提供に支障がない場合は、本体施設の設備を利用できる | 本体施設で必要とされる設備を有することで可 | |
開設方法
- 実施主体(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)は、「併設型」「空床利用型」のどちらの携帯で行うか決める
- 指定申請
- 自治体に相談
- 定款の修正、書類作成
- 自治体の書類確認
- 書類提出
- 審査
- 指定
- 事業開始
報酬・加算
| 施設 | 病院(7:1看護) | 病院(7:1看護)、診療所、介護老人保健施設、介護医療院 | ||
| 利用者 | 療養介護対象者、重症心身障害児 | 慢性意識障害者・児、筋萎縮性側索硬化症との疾患を有する児者等 | ||
| 利用形態 | 1日 | 医療型短期入所サービス費(Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) |
| 2,907単位/日 | 2,703単位/日 | 1,690単位/日 | ||
| 日中のみ | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |
| 2,785単位/日 | 2,571単位/日 | 1,588単位/日 | ||
| 夜間のみ | (Ⅳ) | (Ⅴ) | (Ⅵ) | |
| 2,027単位/日 | 1,893単位/日 | 1,217単位/ | ||
緊急時の重度障碍者の受入れ機能の充実
地域生活支援拠点等である場合の加算
地域生活支援拠点等として、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算。加えて、平時から利用者の生活の状況等を把握するため、指定短期入所事業所等の従業者のうち、市町村及び期間相談支援センター等の連携及び調整に従事する者を1以上配置し、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児・者又は強度行動障害を有する児者に対し、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用をした日について、1日につき所定単位数に200単位を加算。
| 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) | 270単位/日 |
| (Ⅱ) | 500単位/日 |
福祉型強化短期入所サービス費における日中支援サービス類型の創設
福祉型強化短期入所サービスにおいて、医療的ケア児者の入浴支援等、日中の支援ニーズに応えるサービス類型
※医療的ケア児者に対し、看護職員を常勤で1人以上配置している事業者において、日中のみの指定短期入所を行った場合につき、1日につき書体単位数を算定
| 障害者 | 区分6 | 1,107単位/日 |
| 区分5 | 977単位/日 | |
| 区分4 | 846単位/日 | |
| 区分3 | 784単位/日 | |
| 区分1及び2 | 715単位/日 | |
| 障害児 | 区分3 | 977単位/日 |
| 区分2 | 816単位/日 | |
| 区分1 | 714単位/日 |
医療的ケア児の受け入れ体制の拡充
福祉型短期入所サービスについては、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合、障害支援区分5,6の障害者を多く受け入れている場合
| 医療的ケア対応支援加算 | 120単位/日 | |
| 福祉型短期入所サービス費を算定している事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上、医療的ケア児者に対し、指定短期入所等を起こった場合 | ||
| 重度障害児者対応支援加算 | 30単位/日 | |
| 区分5、6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該事業所等の利用者の数に50/100を乗じて得た数以上である場合 | ||
医療型短期入所における受入れ支援の強化
医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対し、利用する前から、事前に自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合
※イについて:事業所の職員が、理療を希望する医療的ケア児者に対し、当該事業所を利用する前日までに、自宅等へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、当該事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について
※ロについて:テレビ電話装置等を活用することにより、 〃
| 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ) | 1,000単位/日 |
| (Ⅱ) | 単位/日位/日 |
医療型短期入所サービスの指定申請事務の負担軽減
障害者総合支援法施行規則に基づく医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の書類は省略可能
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
- 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容