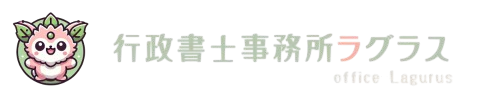自立支援医療制度
医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象者
- 更生医療
- 身体障害者福祉法に基づき身体障碍者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果ができる者(18歳以上)
- 育成医療
- 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に酷化が期待できる者(18歳未満)
- 精神通院医療
- 精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律 第5条
この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害者その他の精神疾患を有する者をいう
利用者負担
| 更生医療・精神通院医療 | 育成医療 | 重度かつ継続 | |
| 一定所得以上 | 対象外 | 対象外 | 20,000円 |
| 中間所得2 | 総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 | 10,000円 | 10,000円 |
| 中間所得1 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 低所得2 | 5,000円 | ||
| 低所得1 | 2,500円 | ||
| 生活保護 | 0円 | ||
| 所得区分(医療保険の世帯単位) | |
| 一定所得以上 | 市町村民税所得割 235,000円以上(年収約833万円以上) |
| 中間所得2 | 市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満(年収約400~833万円未満) |
| 中間所得1 | 市町村民税所得割 33,000円未満(年収約290~400万円未満) |
| 低所得2 | 市町村民税非課税(低所得1を除く) |
| 低所得1 | 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下) |
| 生活保護 | 生活保護世帯 |
※負担上限月額の経過的特例措置
育成医療の中間所得1,2及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和9年3月31日までの経過特例措置
自立支援医療制度・精神通院
通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です
対象者
- 統合失調症
- うつ病、双極性障害などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害
- パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん など
範囲
精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対し、精神通院医療を担当する医師による病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等を含む)
※当該精神障害に起因して生じた病態―精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態
※対象外
・入院費
・公的医療保険対象とならない治療(カウンセリングなど)や投薬の費用
・精神障害と関係のない疾患の医療費
自己負担
- 公的医療保険1割
- 1割負担が過大にならないよう、更に月額負担は世帯の所得に応じて上限額
- さらに高額な治療を長期間にわたり継続(重度かつ継続)で、市町村民税課税世帯の方は通常とは別の月額上限額
受給手続き
市町村の担当窓口に必要書類を提出し、申請が認められると「自立支援医療受給者証」が交付されます。
| 入手できるところ | 注意事項 | |
| 申請書 (自立支援医療支給認定申請書) | 市町村等 | |
| 医師の診断書 | 医療機関 | ・通院中の精神科の病院・診療所で記入してもらう ・「重度かつ継続」の場合、様式が異なる場合がある ※省略できる場合:精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合、前年の申請で診断書を提出した場合など |
| 同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料 ↓ | ||
| 市町村民税課税世帯の場合 | 市町村 | 市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料 |
| 市町村民税非課税世帯 | 市町村 | ・市町村民(住民)非課税証明書 ・ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類 |
| 生活保護世帯の場合 | 市町村又は福祉じゅむしょ | 生活保護受給証明書 |
| 健康保険証(写しなど) | 世帯全員の名前の記載のある被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの | |
| マイナンバーの確認書類 | 個人番号、身元確認ができる書類 | |
※本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」に限られる
※自治体により必要書類が異なる場合がある
有効期間
1年以内(有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合―更新申請)