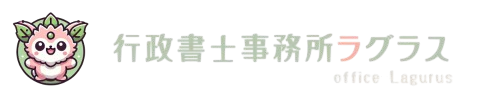障害福祉サービスのイメージと体系
イメージ図
| 医療 | 医療機関 (入院・日常の医療) | <精神科病院> 精神 | 障害福祉 | <事業所・施設> 総合 施設系福祉サービス 通所系福祉サービス 訪問系福祉サービス | |
| 訪問看護事業所 (日常の医療) | 本人・家族 | 地域 | ピアサポート活動 友人 趣味 等 | ||
| <都道府県等> 難病 | 住まいの場 | グループホーム 総合 | 雇用・就労 | <障害福祉> 就労系福祉サービス 障害者雇用 | |
| 相談支援等 | 相談支援事業所等 | ||||
| <市町村> 基幹相談支援センター 総合 精神保健に関する相談支援 精神 | |||||
体系
| 市町村 | 介護給付 | 訪問 | ・居宅介護(ホームヘルプ) 身体介護・生活援助 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 |
| 日中活動 | ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 | ||
| 施設 | ・施設入所支援 | ||
| 訓練等給付 | 居住支援 | ・共同生活援助(グループホーム) ・自立生活援助 | |
| 訓練・就労 | ・自立訓練 機能訓練・生活訓練 ・就労選択支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援 A型・B型 ・就労定着支援 | ||
| 障害児通所支援 | ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 | ||
| 地域相談支援給付 | ・地域移行支援 ・地域定着支援 | ||
| 計画相談支援給付・ 障害児相談支援給付 | ・計画相談支援 ・障害児相談支援 | ||
| 地域生活支援 | ・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム | ||
| 自立支援医療費 | ・更生医療 ・育成医療 ・精神通院医療(都道県等) | ||
| 療養介護医療費 | |||
| 補装具 | |||
| 地域生活支援事業 | ・理解促進研修・啓発 ・自発的活動支援 ・相談支援 ・成年後見制度利用支援 ・成年後見制度法人後見支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具の給付又は貸与 ・手話奉仕員養成研修 ・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム ・移動支援 | ||
| 都道府県 | 地域生活支援事業 | ・専門性の高い相談支援 ・広域的な支援 ・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 ・意思疎通支援を行う者の派遣に係る調整連絡 等 | |
| 障害児入所支援 | ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 |
※身体障害者手帳をお持ちの方で、下記のいずれかに該当して要介護等の認定を受けた方は、介護保険サービスの対象となります。
。65歳以上で要介護等の状態にある方
・40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護等の状態となった方

| 通所系 | 施設へ通う | ・生活介護(デイサービス) ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労選択 ・就労移行 ・就労継続(A型・B型) |
| 児童通所 | ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問 | |
| 訪問系 | 居宅に来てくれる | ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 |
| 居住支援系 | 施設に住む | ・自立生活援助 ・共同生活援助(グループホーム) |
対象者
- 身体障害児・者
- 知的障害児・者
- 精神障害児・者
- 発達障害児・者
- 難病の方・児―難病等の方々で対象疾病に該当する方は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能。児童の場合は、児童福祉法による障害児支援も利用可
- 障害福祉サービス、障害児通所支援、日常生活用具、補装具
- 対象となる疾病→
サービスの利用
- 1受付・申請
サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請
心身の状態、生活環境、介護の状況、サービス利用の意向などの聞き取り - 2障害支援区分の認定
介護給付―障害支援区分の認定
(訓練等給付―一定の場合は障害支援区分が必要) - 3サービス等利用計画の作成
市町村は、申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求める
利用者は、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出 - 4支給決定
市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定
- 5サービス担当者会議
「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催
- 6支給決定(受給者証交付)
サービスの種類、利用料を決定し、受給者証の発行
- 7支給決定時のサービス等利用計画の作成
サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成
- 8サービス事業者と契約
サービスを受ける事業者を選択し、契約を締結
- 9サービス利用の開始
サービス利用が開始
- 10支給決定後のサービス等利用計画の見直し
一定期間ごとのモニタリング
※障害支援区分―障害の特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分
※身近な地域に「指定特定相談支援事業所」がない場合等、それ以外の者が作成した「サービス等利用計画案」を提出することもできます。
※障害児を対象としたサービスについて
・居宅サービス―障害者総合支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利用計画案」を作成
・通所サービス―児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」「障害児支援利用計画案」を作成
・入所サービス―児童相談所が判断を行うため、「障害児支援利用計画」の作成は不要
利用者負担
負担上限月額
所得に応じて負担上限月額があり、ひと月に利用したサービス料に関わらず、それ以上の負担はありません。
| 区分 | 世帯の収入 | 負担上限月額 | |
| 一般2 | 下記以外 | 37,200円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円、障害児は28万円未満) | 施設入所、グループホーム利用以外の障害者 | 9,300円 |
| 施設入所以外の障害児 | 4,600円 | ||
| 20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | ||
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1を除く) | 0円 | |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | 0円 | |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
※所得を判断する際の世帯の範囲
・18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く―障害のある方とその配偶者
・障害児(施設に入所する18、19歳を含む)―同一世帯に属する方(住居及び生計を同一とする者)
<障害児>
| 区分 | 世帯の収入 | 負担上限月額 | |
| 一般2 | 下記以外 | 37,200円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
※3歳児~5歳児入所支援
―(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)及び障害児通所支援(児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)の利用者負担は無償
<高齢障害者>
・一定の高齢障害者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減
自立支援医療
減免
療養介護を利用する場合(医療型個別減免)
- 療養介護を利用する方―従前の福祉部分負担相当額+医療費+食事療養費→上限額の設定
- 20歳以上の入所者―低所得の方は、少なくとも25,000が手元に残るように、利用者負担額が減免
食費等実費負担の減免
<20歳以上の入所者場合>
・入所施設の食費・光熱水費の実費負担―上限55,500円として施設ごとに設定
・低所得者―上記をしても少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付
・就労等により得た収入―24,000円までは収入として認定されず、24,000円を超える額については、来れる額の30%は収入として認定しない
<通所施設の場合>
・低所得、一般1-食材料費のみ負担。額は施設が設定
グループホームの家賃助成
<重度障害者等包括支援の一環を含むグループホーム>
生活保護・低所得―家賃を対象とし、一人当たり月額1万円の上限で補足給付
医療型障害児入所施設を利用する場合(医療型個別減免)
・医療型施設に入所、療養介護を利用する方―従前の福祉部分負担相当額+医療費+食事療養費→上限額の設定
・20歳未満の入所者―地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免
福祉型障害児入所施設を利用する場合
・20歳未満の入所者―地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)と同程度の負担となるように補足給付
児童通所支援の場合
食費負担の軽減
<児童通所支援>
| 区分 | 食費 |
| 一般2 | 11,660円 |
| 一般1 | 5,060円 |
| 低所得 | 2,860円 |
<児童発達支援>
| 事業所費14.4万円 | 利用者負担 | 食費 |
| 一般2 | 14,400円 | 11,660円 |
| 一般1 | 4,600円 | 5,060円 |
| 低所得 | 0円 | 2,860円 |
高額障害福祉サービス費(世帯単位の軽減措置)
| 世帯での合算額が基準を上回る場合 | 高額障害福祉サービス等給付費が支給 |
| 障害者の場合 | 障害者と配偶者の世帯で障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用の場合、介護保険額も含む)の合算が基準額を超える場合(償還払いの方法による) |
| 障害児の場合 | 障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを合わせて利用している場合は、利用負担額の合算がいずれか高い額を超えた部分について |
| 同一の世帯に障害福祉サービスを利用する障害者等が複数いる場合 | 利用者負担の合計額が一定の額を超える場合 |
| 障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する者がいる場合など | |
| 自立支援医療 療養介護医療 肢体不自由児通所医療 障害児入所医療 | 対象外 |
補装具の支給
対象者
- 身体障害児・者
- 知的障害児・者
- 精神障害者・難病等の方児
・補装具購入等の費用を支給する制度
・支給決定は申請に基づき市町村が行う
・補装具費の「借受け」―短期間での交換が必要であると認められる場合など
・負担軽減措置を講じても、自己負担をすることにより、生活保護の対象となる場合―生活保護の対象とならない額まで負担上限月額を引き下げる
・世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上いる場合―公費負担の対象外
| 区分 | 世帯の収入 | 負担上限月額 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |