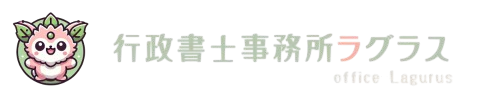「親なき後」の不安に寄り添います
障がいのあるお子さまを持つご家族にとって、「自分がいなくなったら、この子はどう生きていけるのだろう…」という思いは、とても大きな心配ごとです。
当事務所では、その不安を少しでも軽くし、お子さまが安心して暮らしていける未来を一緒に考えます。
遺言や後見制度、信託などの仕組みを活用し、親なき後もお子さまの生活や財産が守られるよう、ひとつひとつ丁寧にサポートします。
「話してよかった」と思える時間になるよう心がけています。
まずは、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
親なき後への備え
障害のある方が親を失ったあとも、安心して暮らし続けるためには、事前の備えがとても大切です。
将来への不安を少しでも軽くし、本人と家族が安心して前を向けるよう、今からできる準備を一緒に考えてみませんか。
1. 生活資金の確保
将来の生活に不安を抱えないよう、今から資金計画を立てることが大切です。
預貯金や保険の活用、信託制度の検討などにより、安心して暮らせる基盤づくりを進めましょう。
2. 住まいの確保
安心して暮らせる場所は、将来の大きな安心につながります。
公営住宅やグループホーム、サービス付き住宅など、選択肢を早めに調べておくとよいでしょう。
3. 支援者・相談先の確保
親以外にも頼れる人・場所を持つことが安心につながります。
行政・地域の相談窓口、支援者や信頼できる親族・友人とのつながりを意識しておきましょう。
4. 生活・医療・介護サービスの把握
日常生活の支援や医療体制を整えておくことで、親がいなくても安心です。
福祉サービスや医療機関の情報を整理し、緊急時にも困らない体制を作りましょう。
5. 権利擁護・成年後見制度の検討
判断力が低下した際に、財産や生活を守ってくれる制度を利用できます。
成年後見制度や任意後見契約を、早めに相談しておくことが将来の安心につながります。
6. 家族・親族との話し合い
将来の生活の方向性や希望を家族で共有することが、トラブル防止につながります。
本人の意思を尊重しながら、みんなで話し合っておくことが大切です。
7. エンディングノート・引き継ぎ資料の作成
支援に必要な情報を整理して残しておくことで、周囲のサポートがスムーズになります。
医療情報や日課、本人の好みなど、細かな情報を記録しておくと安心です。
対策
生活資金
障害年金
生活保護費
公的手当
就労
就労移行支援
働くために必要な就労スキルを学ぶための支援。
就労継続支援A型
事業所と雇用契約を結び、継続的に働く。
就労継続支援B型
雇用契約はなく、工賃という形で賃金を受け取る。
障害者雇用枠
企業の中で、法律で定められている障がい者の採用枠で働く。
特例子会社
障害者の雇用促進と安定した障害者雇用の確保を目的に設立された会社で働く。
後見制度
財産管理や身上監護の支援制度です。
遺言
通常、相続が発生すると遺産分割協議を相続人全員で行うことになります。
このとき、相続人に判断能力がない人がいる場合、その人に成年後見人をつけないと話し合いができません。
成年後見人をつけるには、家庭裁判所への申し立てが必要になり、時間がかかります。
遺言書があれば、遺言内容に沿うことになるので、遺産分割協議が必要なくなり、成年後見人をつける必要がなくなります。
家族信託
「親亡き後」も安心できる、家族のための新しい仕組み
家族信託は、そんな想いに応えるための新しい財産管理の方法です。
親御さんが元気なうちに、ご自分の財産(預貯金や不動産など)を信頼できるご家族に託し、
将来も安心して生活できる仕組みを今から準備することができます。
成年後見制度とは異なり、ご家族の希望に合わせた柔軟な設計が可能です。
例えば、
生活費や医療費を必要なタイミングで管理・支出できる
将来的な相続争いを防ぐ
財産がきちんと本人のために使われるようにする
といったことが可能になります。
「親として最後まで守りたい」という想いを、形にする方法のひとつが家族信託です。
住まい
グループホーム
共同生活を送りながら、専門スタッフによる支援が受けられる場所です。
比較的自立度の高い障害者が対象で、生活のサポートや相談などが受けられます。
施設入所
障害者支援施設など、より専門的な支援が必要な人が入所する場所です。
24時間体制で介護や医療ケアが受けられます。
自宅
親と同居していた自宅で、引き続き生活する場合です。
家族のサポートや、訪問介護などのサービスを利用しながら生活を継続することができます。
自治体の相談窓口
市区町村の障害福祉担当課
行政的な手続き
基幹相談支援センター
地域の中で安定した生活を送れるよう支援の方向性を考えてくれ、他の相談事業所、医療機関などと連携しています。
相談支援事業所
福祉サービスの具体的で専門的な支援を行います。