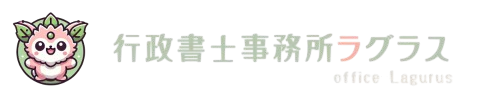障がいのある方とご家族のために、安心してご相談いただける支援を行っています。
手続きの複雑さや制度のわかりにくさに不安を感じていませんか?
当事務所では、ご本人の状況に寄り添い、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
各種手続き、福祉制度の活用、成年後見制度など、お気軽にご相談ください。
特定難病医療費助成申請
指定難病と診断され
①重症度分類に照らして病状の程度が一程度以上
②軽症高額該当(重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある)
に該当された場合医療費助成を受けることができます。
1.支給認定申請書
2.臨床調査個人票
3.世帯全員の住民票
4.保健情報の確認できる書類等
5.課税証明書
6.個人番号調書及び個人番号確認・本人確認に必要な書類
7.収入等を確認する書類
8.同一世帯内に他に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類
9.軽症高額に該当することを証明する書類
10.「高額かつ長期」に該当することを証明する書類
11.境界層該当証明書
12.特定医療費受給者証の写し
障害年金
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
| 対象となる人 | ① 『初診日』に国民年金に加入していた人(20歳から60歳まで強制加入) ② 『初診日』が20歳前の人 ③ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人 | 『初診日』が厚生年金保険加入中にある人 |
特別障害給付金
| 対象となる方 | 1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。 ※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 |
| 必要書類 | 1.特別障害給付金請求書 2.基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 3.障害の原因となった疾病にかかる診断書 4.レントゲンフィルム及び心電図所見のあるときは心電図の写し 5.病歴・就労状況等申立書 6.受信状況等証明書 7.特別障害給付金所得状況届 8.生年月日についての市区町村長の証明書または戸籍の抄本 9.公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類 |
「つなぐ窓口」
―内閣府 障害者差別に関する相談窓口―
電話相談:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
注)メール送信の際には、上記メールアドレス中の「@」(全角表示)を半角に修正してご送信ください。(セキュリティ対策のため文字を置き換えております。)