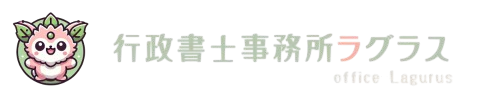グループホーム
グループホームは、まちの中で、ふつうに暮らしたいという障害のある人の思いからつくられてきた制度です。
グループホームは、入居者の家であり、生活の場です。集団生活の場ではありません。あくまでも入居者一人ひとりの暮らしが原点です。
入居者一人ひとりが自分の考えを出しながら、自分の生活をつくっていくところです。
入居者を指導したり、訓練する場ではありません。
元気なときも元気がないときも、得意なことも苦手なことも、入居者のありのままの姿が出せる「暮らしの場」です。
―日本グループホーム学会『グループホーム設置・運営マニュアル』
設置基準
| 介護サービス包括型指定 共同生活援助 | 外部サービス利用型指定 共同生活援助 | 日中サービス支援型指定 共同生活援助 | ||
| 利用者 | 障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食 事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする 者。 (身体障害者は、65 歳未満の者又は65 歳に達する日の前日まで に障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したこと がある者) | 主な対象として、重度化・高齢 化のため日中活動サービス等を 利用することができない障害者 (日によって利用することがで きない障害者を含む) | ||
| 人員 | 管理者 | ・常勤 1人配置 ・兼務可(ただし管理業務に支障がない場合) | ||
| サービス 管理責任者 | ・事業所定員30人以下で、1人配置。 ・世話人又は生活支援員との兼務可、非常勤可(ただし定員20人以上は専従に努める) | |||
| 世話人 | ・兼務可、非常勤可 ・利用者の人数により配置数が異なる※[利用者:世話人]の配置を選択する 6:1利用者数÷6 5:1利用者数÷5 4:1利用者数÷4 (常勤換算方法による) | ・兼務可、非常勤可 ・利用者の人数により配置数が異なる※ [利用者:世話人]の配置を選択する 5:1利用者数÷5 4:1利用者数÷4 3:1利用者数÷3 (常勤換算方法による) | ||
| 生活支援員 | ・兼務可、非常勤可 ・利用者の区分により配置数が異なる 区分3の利用者数÷9 区分4の利用者数÷6 区分5の利用者数÷4 区分6の利用者数÷2.5 の合 計数以上 (常勤換算方法による) | ・配置不要 | 介護サービス包括型と同様 | |
| 夜間支援従事 者 | 特に規定はなし。 | 夜間及び深夜の時間帯を通じて、共同生 活住居ごとに夜勤を行う夜間支援従事者 を(宿直勤務を除く)を一人以上配置。 | ||
| 設備 | 設置場所 | ・住宅地又は住宅と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が保障される地域にあること。 ・入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設若しくは通所により主として日中においてサービスを提供する事業所又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 | ・住宅地又は住宅と同様に入居者の家族や地域住民との交流の機会が保障される地域にあること。 ・入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設、又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 (例えば、同一敷地内に複数の共同生活住居を設置するなど、一定の地域に集約して立地することで、上記に掲げる事項に支障が生じることがないように留意しなければならない) | |
| 居室 | ・1 つの居室の定員は、1 人とすること。 ・居室の面積は、収納設備等を除き4.5 畳(7.43 ㎡)以上(千葉県では6 畳以上を推奨しています。) ※「居室」とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区別されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけでは認められません。 | ・1 つの居室の定員は、1 人とする。 ・居室の面積は、収納設備等を除き4.5 畳(7.43 ㎡)以上 ※「居室」の定義は、介護サービス包括型・外部サービス利用型と同様。 | ||
| 交流を 図る設備 | ・居室に近接して設けられる相互に交流を図ることのできる設備(居間、食堂等) | ・居室に近接して設けられる入居者が相互に交流を図ることのできる設備を設け(居間、食堂等)、その設備については、入居者の状況や介護の支援等を行うことを考慮したうえで、十分な広さを確保する。 | ||
| 台所・便所 浴室・洗面 設備 | ・10 名を上限とする生活単位ごとに区分して配置 | ・10 名を上限とする生活単位ごとに、複数の便所、浴室、洗面所、台所が必要であり、入居者の特性に応じて工夫する。 | ||
| サテライト型 (共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、一人で暮らしたいというニーズに応えたもの) | |
| 給付 | 訓練等給付 |
| 障害支援区分 | 定めなし |
| サービスの内容 | 共同生活援助計画に基づき、定期的な巡回等により、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 |
| 利用期限 | 原則3年 |
| 食事 | 本体住居においての食事、利用者の自炊、どちらも可能 |
| 夜間体制 | 規定なし |
| 設置場所 | 当該住居の入居者が本体住居との間を通常の交通手段で20分以内に移動可能な範囲 |
| 設置個所数 | 定員数4名以下の本体住居に対しては1か所、5名以上の本体住居に対しては2か所が限度 |
| 定員 | 1人 |
| 居室 | ・1つの居室の定員は、1人とすること。 ・居室の面積は、収納設備等を除き4.5畳(7.43㎡)以上。(千葉県では6畳以上を推奨) |
| 交流を図る設備 | 本体住居の設備を利用 |
| 台所・便所・浴室・洗面設備 | ・各設備必要 ・その他、本体住居と適切に連絡が取れる通信機器(携帯電話可) |
| 短期入所 | ・日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(以下、日中サービス支援型)の入居定員のほかに、地域で生活する障害者の緊急一時的な支援に応じられるよう指定短期入所を併設又は同一敷地内に設置する必要があります。併設の場合には、指定短期入所の従業者が日中サービス支援型の夜間支援従業者との兼務が可能です。 ・利用定員数は、日中サービス支援型の入居定員数の合計が、20人又はその端数を増すごとに1以上5人以下となります。 |
| 協議の場の設備 | ・日中サービス支援型を地域に開かれたサービスにすること、サービスの質を確保する目的から地方自治体が設置する協議会等への定期的な報告が必要となります。 ・協議会等に対して運営方針や活動内容などの状況を報告し、評価を受けるとともに必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければなりません。 ・協議会等への報告等の記録は、個人情報の保護に留意しつつ、5年間保存する。また、当該記録や事業の運営状況を積極的に公表するものとする。 |
加算
| 自立生活支援加算 | ||
| Ⅰ | ※居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退去に向け、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、6月間に限り所定単位数を加算。 ※居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算。 ※居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行ったうえで、自立支援協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住居の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合、更に1月につき500単位を加算。 | 1,000単位/月 |
| Ⅱ | 日中サービス支援型のみ | 500単位/回 |
| Ⅲ | 利用期間が3年以内の場合 | 80単位/日 |
| 3年を超えて4年以内の場合 | 72単位/日 | |
4年を超えて5年以内の場合 | 56単位/日 | |
| 5年を超える場合 | 40単位/日 | |
| 以下の要件を満たす事業所において、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退去に向け、一人暮らし等に向けた支援を行った場合 ①利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退去後に1人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1以上有すること ②移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること ③事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援住居に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、かつ、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者が7:1以上配置されていること ④移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。 ⑤移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退去後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害者福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援をp実施すること。 ⑥居住支援法人又は居宅支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。 ⑦居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、自立支援協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。 | ||
| 退去後共同生活援助サービス費、退去後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 2,000単位/月 | ||
| 自立生活支援加算Ⅰ又はⅢを算定していたものに対し、当該利用者の居宅を訪問して以下の要件を満たす内容の支援を行った場合に、退去日の属する月から3月間に限り算定。 ①利用者の一人暮らし等への意向に当たって会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。 ②おおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること | ||
| ピアサポート実施加算、退去後ピアサポート実施加算 100単位/月 | ||
| 次のいずれにも該当する事業者において、障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者である者が、利用者に対して、その経験に基づき相談援助を行った場合に加算。 ①自立生活支援加算Ⅲ又は退去後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費を算定していること ②障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障害者等)配置していること ③②の者により、当該事業所の従業者に対して、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。 | ||
| 人員配置体制加算(介護サービス包括型) | ||
| Ⅰ | 指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で、利用者の数を12で除して得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算 | |
| Ⅱ | 指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で、利用者の数を30で除して得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算 | |
報酬・加算の見直し
| 基本報酬区分(介護サービス包括型) | Ⅰ | 世話人の配置6:1以上 |
| Ⅱ | 体験利用 | |
| 日中支援加算Ⅱ 日中支援対象利用者が2人以上の場合 | ①区分4~区分6まで | 270単位 |
| ②区分3以下 | 135単位 | |
| 個人単位の居宅介護等の利用時の基本報酬 | 令和9年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に所定単位を算定。ただし、所要時間が8時間以上である場合は、所定単位数の95/100を算定。 | |